インタビューInterview

この春、縁あってTOPPANホールにやってきた「1909年製ベーゼンドルファー Model250」。ブラームスの没後からまだそう遠くなく、リヒャルト・シュトラウスがまさに活躍していたさなかに誕生したこの楽器は、音楽の都ウィーンの、文字どおり中心で弾かれたのち、いまは舞台を日本へと変えて物語を紡ぎ続けています。2026年のニューイヤーコンサートは、この特別なピアノを主役に据えて企画。以前からこの楽器をよく知り、今回の公演でもその魅力を伝えてくれる川口成彦さん、兼重稔宏さんに、楽器の得難い個性や公演への意気込みを語っていただきました。
おふたりは東京芸術大学の同級生ですね。お互いの印象からお聞かせいただけますか?
兼重: 川口くんは、全身全霊をかけて作品から魅力的な響きを掬い出すことに喜びを感じている、まさに“ナイスガイ”です。
川口: 兼重くんは、音楽や芸術が本来持つ大事な部分をすごく大切にしていて、それを模索し続けている人ですね。音楽への意識が似ているので、とても親近感をもっています。古楽器の魅力にも意識を向けてくれている人なので、個人的に嬉しいです。
今回“1909年製ベーゼンドルファー Model250”(以下Model250)を借り受けるにあたっては、兼重さんがキーパーソンのおひとりでした。
兼重: ベーゼンドルファーのサロンにはときどき練習に通っていて、あのピアノのことは以前から知っていました。あるべきところにたどり着いたな、と思いましたね。触れるたびに「こんなこともできるんだ!」と、気づきやインスピレーションを与えてくれて、もっとたくさんの人に聴かれるべき素晴らしい楽器だと感じていたので、それを理解してくださるお客さまのいるTOPPANホールで弾かれることになって、本当に嬉しいです。

スタインウェイとベーゼンドルファーは最高峰のピアノとして比較されることが多いですが、それぞれの魅力をどうお感じですか?
兼重: 本質的なことをいうと、ピアノの差とは楽器の個体差で、つまりは楽器をつくった人の個性がいちばん大きな要素だと思っています。本当にいい楽器というのは、メーカーは関係ないのかもしれない。それでもあえて違いを挙げるなら、スタインウェイは全音域でバランスのとれた音色が魅力。イメージしたことがなんでもできると思わせるような期待感、好奇心をそそられるところがあります。一方ベーゼンドルファーは例えるなら、苦手意識を感じていた人でも友人として打ち解けると、その後は長く友情を育んでいけるような…そんな感じに近いところがある。「予想と違う答えが返ってきても、それに耳を傾けたら何かポジティブなことが起こるかもしれない」…そんな風に思わせるのがベーゼンドルファーです。
川口: 楽器も時代を経るなかで、新しく生まれてくるものは素材や作り手の変化を否応なく受けますよね。僕は古楽器を通じて日常的に楽器の歴史をたどっていますが、共通して言えるのは、どの楽器も、その楽器が生まれた時代を映した個性を持っているということです。スタインウェイもベーゼンドルファーも、最近の楽器はやはり“いまの音”がすると感じますね。
それに照らすと、Model250は20世紀初頭を映した個性を持っているということですね。
兼重: そのとおり、まさに音に時代性を感じます。あの時代に生まれたからこそ出てくるのだろう響きが、なんとも素晴らしい。第一次世界大戦がはじまるころ、いまとはまったく違った価値観のなか、ウィーンにおいて芸術がとても大切にされていたことも響きから伝わってくる。ウィーンらしい柔らかさと、どっしりしたボディならではの奥行きある響きが、実に特徴的で味わい深いです。
川口: Model250に初めて触れたのはベーゼンドルファーのサロンで、「なんだこの音色は!」と衝撃を受けたのを覚えています。室内楽的なニュアンスがインペリアルとはまったく違って、シューベルトがシューベルティアーデで演奏していた時代のテイストをすら感じました。室内楽ならではの、お客さまに語りかけるような距離感や、絶妙な表現のニュアンスにこだわりたくなる楽器ですね。古い楽器は、当時の地球環境を反映して年輪が細かい木材でつくられていることがあり、音色に素材からくる密度の高さや独特の香りが感じられます。Model250も、誕生当時の素材のポテンシャルが、音の佇まいから非常に伝わりますね。
この時代の楽器はまだ、製作した職人の顔が見えてくるような印象もあります。Model250をTOPPANホールで弾くことの面白さについてお聞かせください。
兼重: TOPPANホールでは演奏者と聴き手、両方の立場を経験していますが、どちらであっても、音楽との親密な距離感を楽しめるホールですね。Model250の持つ時代性ともマッチした空間は当時のサロンのようでもあります。この楽器にはまだ解き明かされていない部分が多く、神秘的なものが感じられる。今回はブラームスとリヒャルト・シュトラウスの歌曲を演奏しますが、楽器がつくられた1909年はブラームスの没後まだ12年、シュトラウスはまさに同時代を生きていた。ウィーン国立歌劇場で使われていたピアノですから、シュトラウスが弾いていた可能性だって大いにあります。その時代にどういうことが大切にされていたのかを、楽器が直接教えてくれる期待もあります。
人の声との親和性も抜群に高い楽器だと思います。日本ではあまり知られていないかもしれませんが、兼重さんはヨーロッパではよく歌曲を演奏されていたんですよね。
兼重: ドイツでは男声とよくシューマンを演奏していました。歌曲演奏では、物理的に呼吸をしている歌手にあわせて、ピアノを呼吸させる感覚が何より大切。Model250は柔らかい音色が持ち味で、木の温かみからくる豊かな呼吸が可能なので、確かに歌曲と非常に合うと思います。
今回は嘉目真木子さんと初共演です。
兼重: 嘉目さんの歌は以前、北村朋幹くんとのコンサートで聴かせていただき、リリカルで清楚な歌声が印象的でした。Model250とのコントラストでひとつの響きをつくっていくのが楽しみです。リート伴奏者という職業もステキだなと思うくらい歌曲が好きで、ライプツィヒではよく演奏していました。帰国してからはなかなか機会がなくて欲求がたまり続けているので(笑)、待ち遠しくて仕方ありません。作曲家ごとに違う音色が求められるので、その特徴を描き分けていけたらと思います。
ソロでは、ベートーヴェン《ピアノ・ソナタ第30番》を演奏していただきます。
兼重: ベートーヴェンの作品は後期になるにつれて、響きの内実により密度が要求されていきます。Op.109はModel250の特徴である、ウィーンの香りと響きに内包された強さが活かせる作品だと思って選曲しました。第1楽章の、第1主題では軽やかさやハーモニーの美しさ、その香りと強さの対比を、第2主題では内側から捕まえる強さが表現できると思います。「下から積み上げていかないと多層的な響きが出ない」という楽器の特徴を意識しながら、バリエーションがどう変化していくのかに対峙したいです。響きの美しさについ飛びつきたくなるのを我慢して、一音一音、下から丁寧に…密度の高い音楽を生みたいです。

川口さんは、ヴァイオリンの山根一仁さんとの初共演。
川口: 山根くんも古楽に関心があると聞いています。お互いを尊重しながら、それぞれの経験と価値観をディスカッションしながら融合させていけたらいいですね。どんな感じになるかな。
兼重: ふたりとも何をするのか分からないところがあるから、めちゃくちゃ刺激的になりそうだね。
ソロでは、シューベルトとショパンを聴かせていただきます。
川口: ショパンは8か月ほどウィーンに住んでいたことがあって、ウィンナワルツなどのカルチャーに触れています。ワルツを弾くとそのことを強く感じます。ユーモアのセンスもあった人で、《華麗なる大円舞曲》には彼の茶目っ気があふれている。弾いていると、舞踏会で貴婦人が踊る光景が見えてくるようです。実はいま、お芝居的な演奏解釈にチャレンジしていて、小さな喜劇を見ているような、想像力を掻き立てる演奏がしたいと思っています。《夜想曲第2番》はプレイエル夫人に献呈された作品。きっとパリのサロンで弾いていたでしょうから、そこに想いを馳せつつ、「ピアノの詩人」と称された魅力を表現したいですね。TOPPANホールは、ショパンがパリで初リサイタルをした300席のホールと規模感が近い。ロンドンでは900席ほどで、彼のデリケートな音がほとんど聴こえなかったという話が残っていますが、TOPPANホールなら、演奏者のこだわりがお客さまにダイレクトに届きやすいと思います。
シューベルト《4つの即興曲集 D899》は、2022年のニューイヤーコンサートでも弾かれています。
川口: 大好きで思い入れのある曲です。前回はフォルテピアノでしたが、今回はモダンのヴィンテージのベーゼンドルファー。新たに作品と向き合って、この楽器にしか出せない音色を引き出したいですね。
毎回違う楽器を演奏できるのは、ピアニストならではの楽しみでしょうか。
川口: そうですね。同じ作品でも楽器が変わると、テンポ感や音色の届けかたなど、作品が出来上がっていく感覚がまったく違ってきます。だからピアニストって楽しい。大変なときもあるけど(笑)。
兼重: ヨーロッパだと「今日これで弾くんですか!?」みたいなことも多いもんね。本番の2日前に鍵盤がとれてセロテープでとめられていたなんてこともありました(笑)。どこのホールでもクオリティの高いピアノが用意されているのは、日本くらいですね。
2度の大戦を潜り抜けて、Model250が非常にいい状態でいまを迎えているのは奇跡かも知れませんね。多面的なプログラムを通して、きっと楽器のさまざまな個性を感じていただけると思います。
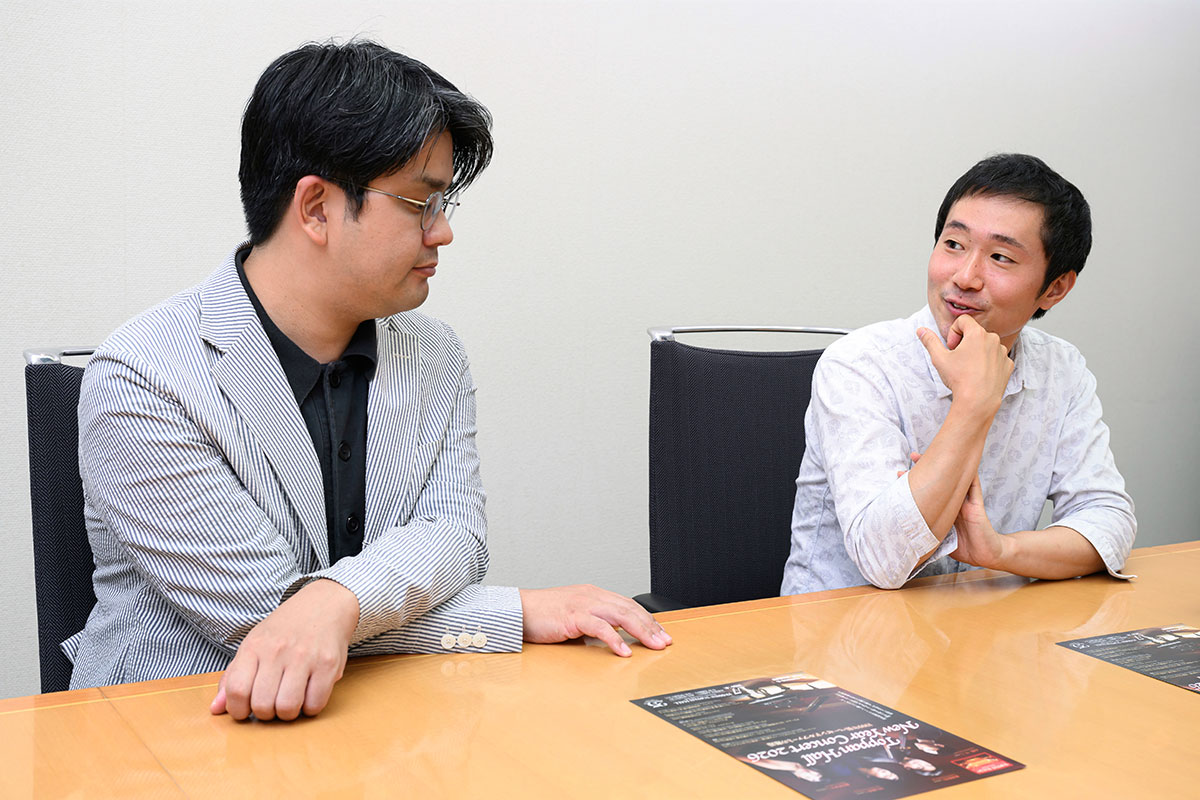
川口: そういえば最近、複数の知人から「いま(第二次)ルネサンスが到来してるよ」と言われたのですが、既成の価値観があちらこちらで崩壊の兆しを見せているいま、コロナ禍も経た人間回帰の流れで、室内楽的なものに魅力を見出す潮流がきている気がします。
兼重: 確かに、親密な空間で質の高い音楽を楽しみたい人は増えている実感がありますね。
川口: どのみち僕たちは、いい音楽を届けることに集中するだけだけど。
兼重: AIにとって代わられないようにね(笑)。『クララとお日さま』(編注:カズオ・イシグロ長編最新作)って知ってる? AIが心を持つ話。
川口: 面白そうだね。でも僕は、AIは本物の価値を上げるものだって、ちょっと前向きに考えてる(笑)。AIのおかげで、生身の人間が音楽をライヴでやる価値は上がると思うよ。
(2025年9月)
TOPPANホール ニューイヤーコンサート 2026
1909年製ベーゼンドルファーとの邂逅
2026/1/7(水) 19:00
山根一仁(ヴァイオリン)/嘉目真木子(ソプラノ)/川口成彦(ピアノ)/
兼重稔宏(ピアノ)


